珍しいオペラの本が出版されました。
オペラはオペラでも「バロック・オペラ」!!
日本のオペラ界の中心的存在の一つ新国立劇場が発行。山田治生、井内美香、片桐卓也、矢澤孝樹氏が執筆された本です。

●よくわからなくても読めちゃう(笑)♪
バロック・オペラの「バロック」は、確か高校時代の音楽の教科書に出てきて「歪んだ真珠」なんて習った記憶がありませんか?
まだまだ音楽の形式が整わなかったからなのか、この単語が語源になったようです。ということで、クラシック音楽の中でも古〜い時代、1600年〜1750年頃の音楽は「バロック音楽」と呼ばれています。
建築とか、絵画などでも「バロック様式」っていう区分がありますよね。
そんな「バロック音楽」の中の「オペラ」。実のところ私的にはほとんど知らない分野でピンときません^^;
 作曲者の名前は、
作曲者の名前は、リュリとか →
ラモーとか
ヴィヴァルディ等々
オペラの作曲家としてではなく
知っている名前を見つけることは
出来たのですが、大半が知らない名前が
連なっていました。
例えば…
ニコラ・ヴィート・ピッチンニ…?!
ピッチンニって台所用品にありそうな名前だなぁとか^^;
当然のことながら、オペラの名前を見ても聞いたことがないようなものばかり^^;;
「アッキーナ」なら知っているけど…「チェッキーナ」なんていうオペラは聞いたことがありません(笑)。
そんなド素人な感覚でこの本を読んでわかるのだろうか…? って思ったのですけれど(笑)。
1つのオペラに対して、1ページにまとめられた「概説」と「あらすじ」という構成になっているので、これが意外にも簡単に読めちゃうんですよ! しかもへぇ~、そういうオペラなんだ~って何となくイメージまで出来ちゃう。わからない人にも見えてくるってすごい本じゃないですか?

あと、オペラの作曲家たちが、イタリア、フランス、ドイツ、イギリスに振り分けられていて、作曲家の生年順に掲載されており、それぞれの国のバロック・オペラの特徴やその国の主な作曲家たちの解説が載っているのもとても親切でわかりやすい構成じゃないかと思います。
●カストラートって知っていますか?…
間にコラムが挟まっているのですが、これがまた興味深い内容になっているのですよね。
そのコラムのタイトルがこちら。 ↓
オペラの誕生
カストラート
ヴェネツィア楽派
詩人ピエトロ・メタスタージオ
ナポリ楽派
インテルメッゾ
バロック・オペラの現代的な演出について
機械仕掛けの神
オペラのオーケストラの変遷
バロック・オペラの劇場
サンクトペテルブルクのオペラ事情
例えば…「カストラート」というのは、去勢された男性歌手のことなんです。

変声期前の声を保つためにやっていたそうですよ。「カストラート」という言葉は知っていましたが、本当にそんなことをしていたのかしら? って思っていました^^;
●バロック・オペラを聴きたくなったよ♪
本を読んでいるうちに、いったいどんな音楽なんだろう…って興味が湧いてきました。手軽に聴けるのは、YouTubeですが、探すのにコツがあるようです。作曲家とタイトルは原語で入れた方がヒット率が高いみたい。
ちなみに、史上最初のオペラと言われている「エウリディーチェ」(ペーリ作曲)は、Peri / Euridice こんな感じで検索をかけるとヒットします。

とはいえ、ただyoutubeで聴いているだけよりも、やっぱりそのオペラの背景を知ったり、あらすじを知って聴くのとでは、楽しめる度数は段違いじゃないかと思います♪ ということで、この本、オススメ!!(笑)
在庫少なめなようです。セブンネットで残りわずか、アマゾンでは高値がついているようです。
「バロック・オペラ その時代と作品」
山田治生/編・著 井内美香/著 片桐卓也/著 矢澤孝樹/著
出版社名:新国立劇場運営財団情報センター
ISBN:978-4-907223-04-5
発売日:2014年03月
販売価格:本体700円+税
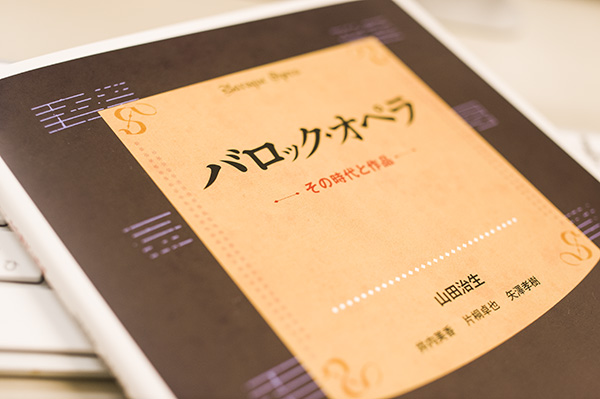
コメント
バロックのオペラは聴いたことがありません。
興味津々 ^^
カストラートは映画でありましたよね、これも興味があったので、昔、見に行ったことがあります。芸術のためとはいえ、ちょっと、びっくりしました。
本、面白そうです。読んでみます。 ^^
>mozさん
こちらまでありがとうございました!
バロック・オペラって私も演奏会などで聴いたことがありません。今回youtubeで探して聴いてみたくらいです^^;;
そういえば、ありましたね! 「カストラート」という映画。あれ私は観ていないのです。昔の人もここまで突き詰めて音楽を求めていたということに驚きを覚えます。